『建築家は住まいの何を設計しているのか』藤山和久(筑摩書房)
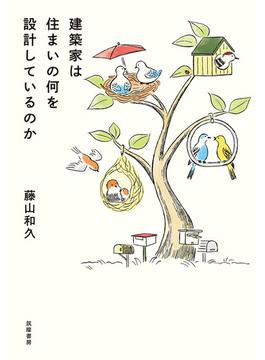
建築というものに漠然とした興味は常に持っているので、本書も自然と手にとったのだが、「建築家」「設計」といった単語から想像するような大仰なテーマではなく、「住宅設計に関する小話の集まり」で、筆者も「住宅業界の関係者なら、いずれもおなじみの話ばかりだったかと思います(意見の相違はあるかもしれませんが)」と語っている。実際に自分で家を建てたことがあれば、それらへの親近感や切実さもあるだろうが、そうでなかったとしても誰もが「住まい」で暮らしている以上、すべての話題が結局は身近に思えてくる。翻ってみれば現在の自分の住まいの強みや弱みが浮かんで来ると同時に、住まいに対する自らの判断基準が相対化され、生活全般に対する認識そのものを見つめ直す好機にもなった。
本書全体に通底しているのは、今や常識(的)となった住宅設計のあれこれに対する疑いや抵抗。それはただ単に興味を引くための煽りではなく、一般化した常識がいかに実際的な意義を生み出さない「最大公約数」であるかという指摘。とにかく効率化をひたすら目指す現在の住宅設計において、「機能性を高めるネジを少しだけゆるめてやれば、それまで見えなかった景色も見えてくる」(46頁)といった提案なのだ。
「広いリビングなんて、たんなる見栄の産物なんですよ」という建築家の指摘が紹介されている。実際の生活においても当てはまる事例は多くあるだろうが、そもそも日本のドラマや映画においてもリビングで住人たちのドラマが進行することは極めて少ないように思う。家族であれば、その多くは食卓で展開されるし、むしろリビングとそれ以外の空間に分散している様相こそがリアルな家族の光景として描かれる。家族がリビングに会している場面はむしろ、異常事態の象徴だったりする。しかし、日本の住宅状況を反映させるため、ドラマや映画にも「広いリビング」は(物理的には)登場する。
ある建築家が明言する、住居を設計するうえで必須の「三つのS」が興味深い。
一つ、スッキリ(Sukkiri)させること。
一つ、スマート(Smart)にできること。
一つ、スペシャル(Special)があること。(104頁)
スッキリは収納スペースの十分な確保、スマートは高機能な設備機器の導入。それらは常識的な住宅設計の場面でも頻出する話題だろうが、真に満足できるかどうかを左右するのが三つめのSだという。「その家だけの特別な何か」をつくることが、その家への満足が高いまま維持される秘訣なのだ。そうした発想は、家づくりに限らずあらゆるものにも当てはまるように思う。
本書にはさまざまなエピソードが紹介されているが、そうした具体性に触れるたび、自分が使い続けるものを選んだり作ったりするというのは、まずは自分の持つ特殊性を見極め、その特殊性と最も相性の好い選択をすることなのだと実感した。家は住むためのものであり、そこでどのように暮らすかは人それぞれだ。暮らしている人自身も時間と共に変化する。が、変化しないところだってある。それらの要素と向き合ったなら、「天井は高い方がいい」「リビングは広い方がいい」「○○はあった方がいい」「明るい方がいい」等々、一概に単純に決定できることなど一つもないはずだ。
自由に設計しようとする施主に限って、流布している価値観に基づいた選択の寄せ集めのようになってしまいがちだという指摘がある。それが自身にとって最適でなかったとしても、依頼された側はクレーム対策として言われるままに施主の「自由」を尊重しようとすることが多いとも。自覚なき自由からの逃走のような事態を回避するためには、信頼できる〈権威〉との対話が必要なのかもしれない。
『瞬間』ヴィスワヴァ・シンボルスカ(未知谷)

1996年にノーベル文学賞を受賞したシンボルスカが、受賞後はじめて出版した詩集が本作だという。どの詩も静謐さと重厚さをたたえながら、軽やかな語りを拒んでもいない。
裏表紙にも印刷されている「とてもふしぎな三つのことば」は、三つの文から成る。
「未来」と言うと
それはもう過去になっている。
「静けさ」と言うと
静けさを壊してしまう。
「無」と言うと
無に収まらない何かをわたしは作り出す。
言葉の持つ力、その力を持て余し、翻弄される人間の悲しみを思う詩集最後の一篇「すべて」では、「すべて」という言葉を使う人間に対して次のように記している。
何ひとつ見逃さず
集めて抱え込み、取り込んで持っているふりをしている。
ところが実際には
暴風の切れ端にすぎない。
私が一番好きな詩は奇しくも、訳者の沼野充義氏と同じだった。その「魂についての一言」には、次のような一節がある。
喜びと悲しみ
これは魂にとって別々の感情ではない。
この二つが合わさったとき初めて
魂は私たちの中に宿る。
魂をあてにすることができるのは
私たちが何事も自信が持てず
なんでも面白いと思うとき。
私たちに容易く居ついてくれない魂なのだが、それでは魂とは私たちにとって絶対的な支配者なのかというとそうではない。
どこからやって来たのか
どこに消えていくのか、教えてくれない
でもそういう質問を明らかに待っている。
どうやら
私たちが魂を必要とするのと同様に
魂のほうも
私たちを必要としているようだ。
魂は人間を超越し、人間とは区別されたものではなく、人間がいることによって在るものなのだろう。そして、それは言葉も同じであり、人間が生みだしたものでありながら、人間を超えている。しかし、人間がいなければ在りえない。ところが、人間が魂や言葉にとって完全な存在になり得ることもない。
本書には、詩一篇ごとに沼野氏による「解題」が付されているのだが、単なる解説や翻訳ノートに留まらず、沼野氏自身の考察や想いが些か直情的に記されており、詩を読んだ後に互いの感想を語らっているような気分を味わえる。そしてもう一度、詩を読み返す。今しかない「瞬間」に、未来が過去となる豊かさを味わう。
『体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』伊藤亜紗(文藝春秋)

本書の目的は、「できるようになる」ことの不思議さや豊かさを改めて想起させ、能力主義(「できる=すぐれている」「できない=劣っている」といった価値観)によって奪われてしまった「できる」の醍醐味を取り戻す。そのために五名の研究者(古屋晋一、柏野牧夫、小池英樹、牛場潤一、暦本純一)との対話を通じて筆者が気づいたり考えたりしたことが記されている。それらの内容の原点として、筆者は次のような事実を重視する。
結論からいえば、私たちは、自分の体を完全にはコントロールできないからこそ、新しいことができるようになるのです。(8頁)
「できなかったことができるようになる」とは、端的に言って、意識が体に先を越される、という経験です。つまり、「できるようになる」の中に、すでに「負け」があるのです。不意にできてしまってから、「ああ、なんだ、そういうことか」と分かる。本書で具体的な事例を通して見ていくように、困難なことができるようになるとき、意識はあとから遅れてついていっています。(11-12頁)
第1章では、体の動きに注目してピアニストの演奏技術を助ける方法を研究している科学者・古屋晋一の活動が紹介されている。エクソスケルトンという器具を手に装着することで、本人の意志と切り離して指を動かすことのできる。その経験によって、器具を外した後も本人の技術に向上が見られるという。「こうすればうまくいく」(といった既存のイメージ)の外に対する感度を高め、一度も成功したことがなかったからこそ持てなかった動作のイメージを与えることで、イメージすることのできなかった領域へと体を連れ出す。そして、体に先を越された意識は「あ、こういうことか」という感想に至る。
技術偏重の古いピアノ教育においては、体を透明化することが目指されてきたという。「音楽をさまたげない体」が良しとされ、「その体だからこその音楽性」は求められない。しかし、ショパンが残した次のような言葉が紹介されている。「指の力を均等にするために、今までに無理な練習がずいぶんと長い間行われてきた。指の造りはそれぞれに違うのだから、その指に固有なタッチの魅力を損なわないほうがよく、(・・・)逆にそれを十分生かすよう心がけるべきだ」。
一般化や普遍化を通じて得られる知識や技術こそが科学の根幹を支えているとはいえ、そうした発想を前提に身体そのものと接するならば、個別の身体に対して均質や模範を見いだそうとする思考からは免れ得ないだろう。そして、身体活動を考える際にも、身体のもつ固有性より、一般的(模範とされる)身体が産み出す活動が「あるべき」形として提示される。それは「その体」が為し得る最高の活動なのだろうか。素晴らしい歌が「その声」を活かしたものであるように、素晴らしい演奏も「その指」「その体」を活かしたものであるはずなのだと改めて思えた。
第2章では、桑田真澄のピッチングフォーム解析から話が始まるのだが、同じように30回投球してもらった結果、その投球フォームは毎回違っていた。1球目と30球目では、リリースポイントが水平方向に14センチもずれていた。しかし、球が飛んでいった先ではキャッチャーが構えたところに同様に届いている。つまり「重要なのは「パフォーマンスが毎回同じ」(機械的な再現性)ではなく、「結果を同じにするためのパフォーマンスを変える」(変動の中の再現性)」なのだという。哲学者のヒューバート・L・ドレイファス曰く「上級者段階の行動は合理的、プロは過渡的、エキスパートは没合理的」(『純粋人工知能批判』)なのだ。
第3章、第4章でも興味深い研究内容や技術的成果の説明が続き、第5章では研究から導き出される(本書全体を包括するような)身体論が展開されている。身体がもつ自己性と他者性の往来、狭間、関係性がもつ多様な不思議と発見が、事実に基づきつつも、思考の汎用性をもって語られる。筆者も志向する文理共創的なアプローチが、自然な気づきと個人的な好奇心を伴いながら試みられていく。
能力主義が退屈なのは、「できる/できない」を優劣として考えてしまうからだけでなく、「できる=すぐれている」「できない=劣っている」という思考の持つ硬直、静的な視点にあるのかもしれない。人間が生きるとき、そこで起こるべきは動的な「できるようになる」だし、「できないようになる」という動的変化だってあるはずだ。人間の身体が変化と共にあるという現実は、「できる」の形が変化するという事実を生み、その事実から私たちは自分のなかに流れている時間を識ることができる。自らの脳が知り尽くすこともコントロールすることもできない領域が大きい身体のリアルを、テクノロジーという外部化した人間のもう一つの脳の営為が教えてくれる。そもそも、人間ができることとできないこととの線引き自体曖昧、いや無用なのかもしれない。